ニコライ・ロスラヴェッツ
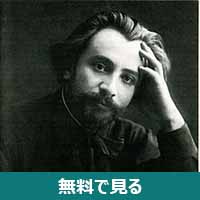
ニコライ・アンドレーヴィチ・ロスラヴェッツもしくはニコラーイ・アンドレーエヴィチ・ロースラヴェツ(ロシア語: Никола́й Андре́евич Ро́славец, ラテン文字転写: Nikolai Andreevich Roslavets, 1881年1月4日 ロシア帝国/チェルニゴフ県スラージ – 1944年8月23日 ソビエト連邦/モスクワ)は、ソ連建国期の重要なモダニズムの作曲家・音楽理論家。ロシア・アヴァンギャルドの作曲家の一人として前衛的な創作活動を行い、ソ連揺籃期において、西側の新音楽を積極的に擁護した。また、シェーンベルクとは別に、ロシアにおいて独自の十二音技法を発展させた作曲家であると見られたこともあるが、彼の作曲技法を「十二音技法」とするのは適切ではない、という指摘もあり、現在ではそのような見方は一般的ではなくなっている。小品を含めて数多くの室内楽曲(5つの弦楽四重奏曲、6つのヴァイオリン・ソナタ、2つのヴィオラ・ソナタ、2つのチェロ・ソナタ、5つのピアノ三重奏曲など)を遺したほか、2つのヴァイオリン協奏曲と、5つの交響詩(うち3曲は紛失)を手懸けている。1930年代以降は弾圧された。
ロスラヴェッツによる3つの自叙伝は、互いに食い違っている。そのうち1924年に出版されたものは、「プロレタリア音楽家同盟」から攻撃されまいとして、自身の生涯をかなり脚色している。公文書の史料によると、ロスラヴェッツはドゥーシャトゥイン(Duszatyn)生まれでもなければ貧農の出自でもなかった。1890年代はコノトプやクルスクの鉄道で駅員として勤務し、クルスクのアルカディ・アバザの音楽教室でヴァイオリンやピアノ・音楽理論・和声法を学んだ。1902年に入学許可を得てモスクワ音楽院に進み、ヴァイオリンをヤン・フジマリーに、作曲法をセルゲイ・ワシレンコに、対位法・フーガ・楽式論をミハイル・イッポリトフ=イワノフとアレクサンドル・イリインスキーに師事。1912年にバイロンの劇的な韻文『天と地』に基づく神秘劇により銀メダルを得て音楽院を修了した。
1910年代においてロスラヴェッツの作品はロシア未来派の機関誌において発表され、数点の楽譜が未来派の美術家によって装幀された。1917年以降は、アルトゥール・ルリエーやカジミール・マレーヴィチ、フセヴォロド・メイエルホリドらとともに、ロシアにおける「左翼芸術」の最も著名な人物の一人となった。イェレーツやハルキウ、モスクワでヴァイオリンや作曲法の教師を務め、ハルキウ音楽学校の校長にも就任した。国立出版局に職を得て、雑誌『音楽文化(ロシア語: Музыкальная Култура)』を編集し、またソ連現代音楽協会(ACM)の指導者のひとりとなった。
| 基本情報 | |
|---|---|
| 出生名 | ロシア語: Николай Андреевич Рославец |
| 別名 | ウクライナ語: Микола Андрійович Рославець |
| 生誕 | 1881年1月4日 |
| 出身地 | ロシア帝国、スラージ |
| 死没 |
1944年8月23日(63歳没) ソビエト連邦 ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国、モスクワ |
| 職業 | 作曲家・音楽教師・音楽理論家・音楽評論家 |
反応