パウル・グレーナー
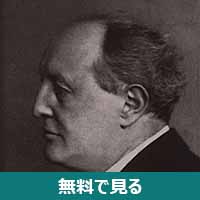
パウル・ヘルマン・フランツ・グレーナー(Paul Hermann Franz Gräner, 1872年1月11日 – 1944年11月13日)は、ドイツの作曲家・指揮者。
ベルリンのベルト職人の家庭に生まれた。1881年にボーイソプラノとして聖歌隊入りし、1884年から1890年までベルリンのアスカーニエン・ギムナジウムに在籍した。1888年には特待生としてファイト音楽院(Veitschen Konservatorium)で教育を受け、作曲をアルベルト・ベッカーに師事した。シュテンダルを振り出しに、ブレーマーハーフェンやケーニヒスベルク、ベルリンで楽長として契約を結び、1898年から1906年までロンドン王立ヘイマーケット劇場の音楽監督に就任するかたわら、英国王立音楽院でも教鞭を執った。後に姓を Graener と表記するようになった。イングランド入りに先立って、マリア・エリザベート・ハウシルト(Maria Elisabeth Hauschild, 1872年 – 1954年)と結婚して3児を儲けた。そのうち、長男ハインツは10歳で、次男フランツ(1898年 – 1918年)は20歳で早世しており、クラーラ(もしくはクレール、1903年生)も30代で夭折した。
パウル・グレーナーは1920年代末より国家社会主義ドイツ文化闘争同盟に入会した。声楽曲のいくつかでは、ドイツ・ロマン主義文学をナチス・ドイツのプロパガンダのために流用しており、例えばフリードリヒ・シュレーゲルの『想い出の歌』(Gesang der Erinnerung, 1807年)による《救い主は遠くない》(Der Retter ist nicht weit) や、テオドール・シュトルムの詩による闘争歌は、その典型にほかならない。
ウィーンに一時期逗留した際に新ウィーン音楽院の作曲法の教員を務め、1911年から1913年まではザルツブルクのモーツァルテウムの院長に就任した。1914年よりフリーランスの作曲家としてミュンヘンに暮らし、1920年から1927年まで、マックス・レーガーの後任の作曲法の教授としてライプツィヒ音楽院で教鞭を執った。1930年に、前年に死去したアレクサンダー・フォン・フィーリッツの後任としてベルリン・シュテルン音楽院の院長に就任。1934年にはプロイセン芸術アカデミーのマスタークラスを監督した。
| 基本情報 | |
|---|---|
| 生誕 | 1872年1月11日 |
| 出身地 | ドイツ帝国ベルリン |
| 死没 | 1944年11月13日(72歳没) ドイツ国 |
| ジャンル | クラシック音楽 |
| 職業 | 作曲家・指揮者 |
反応