島津保次郎
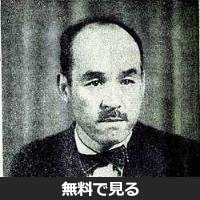
島津 保次郎(しまづ やすじろう、1897年6月3日 – 1945年9月18日)は、大正・昭和期の映画監督。松竹蒲田撮影所で蒲田調と呼ばれる小市民映画を多数製作し、松竹の代表的監督となった。
東京神田区駿河台(現・千代田区神田駿河台)に下駄用材商と老舗海産物商「甲州屋」を営む父・音次郎の次男として生まれる。正則英語学校(現・正則学園高等学校)に入学するが、幼いころから極度の映画好きであった島津は学校をさぼって近くにあった映画館・錦輝館へ行って映画を見ていた。当時から映画監督への道を志しており、逓信省の宣伝映画のシナリオ公募に入選した経験もある。卒業後、実家の手伝いで、福島で下駄用桐材の切り出しに携わる。しかし、松竹が映画事業に乗り出すことを知り、父の友人の紹介で小山内薫の門下生として、松竹キネマ蒲田撮影所に入社する。
1920年、小山内に従って松竹キネマ研究所に移る。同研究所には牛原虚彦や伊藤大輔、村田実らも参加した。翌1921年、研究所第1回作品の『路上の霊魂』で助監督と照明係(クレジット上では光線)を、第2回作品で牛原の監督デビュー作でもある『山暮るる』で助監督を務めた。同年、大阪で『寂しき人々』を撮って監督デビューするが、封切られずじまいに終わっている。
研究所の解散後、蒲田撮影所に復帰。牛原の『剣舞の娘』で助監督を務めたのちに監督として一人立ちする。初めは『遺品の軍刀』などの美談ものを手がけていたが、1923年、ハウプトマンの原作を伊藤大輔が脚色した『山の線路番』で認められ、その写実的な作風で松竹蒲田のトップクラスの監督となった。同年9月1日に関東大震災で撮影所が罹災。京都に機能移転するために多くのスタッフ・俳優が京都に移ったが、島津は東京に残った。そこで城戸四郎が蒲田撮影所の代理所長に就任、彼の主導により『お父さん』『蕎麦屋の娘』を製作。1924年に撮影所が復帰し、その半年後に城戸が正式に撮影所長に就任。城戸の指揮の下、これまでの新派的な作風にかわり、蒲田調と呼ばれるサラリーマンや庶民の日常生活を描く小市民映画が製作されていくが、島津は同年にすでにサラリーマン喜劇の『日曜日』(1924年)などを発表しており、蒲田調の先駆的存在となった。
|
東宝映画社『東宝映画』第3巻第8号(1939)より
|
|
| 生年月日 | 1897年6月3日 |
|---|---|
| 没年月日 | 1945年9月18日(48歳没) |
| 出生地 |
日本・東京市神田区駿河台 (現在の東京都千代田区神田駿河台) |
| 死没地 |
日本・東京都本郷区 (現在の東京都文京区) |
| 民族 | 日本人 |
| 職業 | 映画監督 |
| ジャンル | 映画 |
| 活動期間 | 1921年 – 1945年 |
| 著名な家族 | 島津昇一 |
| 主な作品 | |
|
『隣の八重ちゃん』 『兄とその妹』 |
|
反応